はじめに
「ついつい食べ過ぎてしまう」「ダイエットを続けられない」と悩んでいませんか?
食べ過ぎの原因は単なる空腹だけではなく、心理的な要因も大きく関係しています。
ここでは、心理学を活用して食べ過ぎを防ぐための具体的なテクニックを詳しく紹介します。
難しいものはないので、手軽に始めることができます。
1. 小さなお皿を使う
食べる量を視覚的にコントロールするために、小さな皿やボウルを使うのがおすすめです。
効果の理由
- 大きな皿に少量の食べ物を盛ると、脳が「足りない」と錯覚することがあります
- 小さな皿に適量を盛ると、満足感を得やすい
具体的な方法
- 直径20cm以下の皿を使用する
- 深めのボウルより、平たい皿を選ぶ
- 視覚的に満足できるように盛り付けを工夫する
100円ショップなどでも買うことができるので、お金をあまり使うことなく始めることができます。
2. 食事中に「箸置き」を活用する
食事のペースを落とすことで、満腹中枢を刺激しやすくなります。
満腹中枢とは、脳の視床下部にあって摂食行動を調整する中枢神経。満腹中枢は、血液に含まれる血糖値の上昇に刺激されることにより、食欲を抑制する指令を出す。この指令が大脳に伝わることにより、満腹感が生じ、食べ過ぎを防ぐことができる。
引用元クインテッセンス出版
効果の理由
- ゆっくり食べることで満腹感を得られやすい
- 「ながら食い」を防ぎ、食事に集中できる
具体的な方法
- ひと口ごとに箸を置く
- 30回以上噛んでから飲み込む
- 会話をしながら食べる
3. 食事の前にコップ1杯の水を飲む
食前に水を飲むことで、満腹感を早く感じられます。
効果の理由
- 胃が膨らみ、食事量を自然に減らせる
- 食事のペースがゆっくりになり、食べ過ぎを防ぐ
具体的な方法
- 食事の10〜15分前にコップ1杯(200ml)の水を飲む
- 炭酸水を活用すると、より満腹感が得やすい
- 温かいお茶を飲むのもおすすめ
4. 5分待ってからおかわりする
すぐにおかわりをすると、脳が「もっと食べたい」と錯覚してしまうことがあります
効果の理由
- 満腹感が脳に伝わるまでに約20分かかるため
- 一度リセットすることで、本当にお腹が空いているのか判断できる
具体的な方法
- 食後に5分間何も食べずに待つ
- その間に軽くストレッチや深呼吸をする
- 本当にお腹が空いているか、自分に問いかける
5. 食べる環境を整える
視覚や嗅覚も食欲に影響を与えます。
効果の理由
- 食卓周りの環境を整えることで、食べ過ぎを防ぎやすい
- 鮮やかな青色は食欲を抑える効果がある
具体的な方法
- 青い皿やランチョンマットを使う
- ダイニングの明るさを少し落とす
- 食事中にスマホを見ないようにする
6. 「食べてはいけない」ではなく「食べてもいい」と考える
禁止すると逆に食べたくなる心理が働きます。
効果の理由
- 「食べてはいけない」と思うと、逆に欲求が強くなる
- 罪悪感を感じにくくなり、暴飲暴食を防げる
具体的な方法
- 「このお菓子は食べてもいいけど、半分だけにしよう」と考える
- チートデイを設け、好きなものを食べる日を作る
- 「○○を食べたら××(運動・ストレッチ)しよう」と考える
7. 日記やアプリで食事の記録をつける
自分の食生活を可視化することで、食べ過ぎを防ぐことができます。
効果の理由
- 食べた量を把握することで、過食に気づきやすい
- 無意識の間食を減らせる
具体的な方法
- 「あすけん」や「MyFitnessPal」などのアプリを活用する
- ノートに手書きで食事の内容を記録する
- 写真を撮るだけでもOK
8. 「食べる目的」を明確にする
感情的に食べることを防ぐために、「なぜ食べるのか」を意識しましょう。
効果の理由
- 「本当に空腹なのか?」と自問することで無駄な食事を減らせる
- ストレス食いや習慣的な間食を防げる
具体的な方法
- 「お腹が空いたから食べるのか?それともストレス解消?」と考える
- 本当に空腹なら、野菜やスープを選ぶ
- お腹が空いていないなら、散歩や深呼吸をする
まとめ
食べ過ぎを防ぐには、心理学を活用することが効果的です。
今日からできる簡単な方法
- 小さなお皿を使う
- 箸置きを活用し、ゆっくり食べる
- 食事前にコップ1杯の水を飲む
- おかわり前に5分待つ
- 食べる環境を整える
- 「食べてもいい」と考え、ストレスを減らす
- 食事の記録をつける
- 食べる目的を明確にする
これらのテクニックを取り入れることで、無理なく食生活を改善できます。
ぜひ試してみてください!
無理をすることなく、ストレスを抱えずにダイエットに行うことが一番良い方法です。
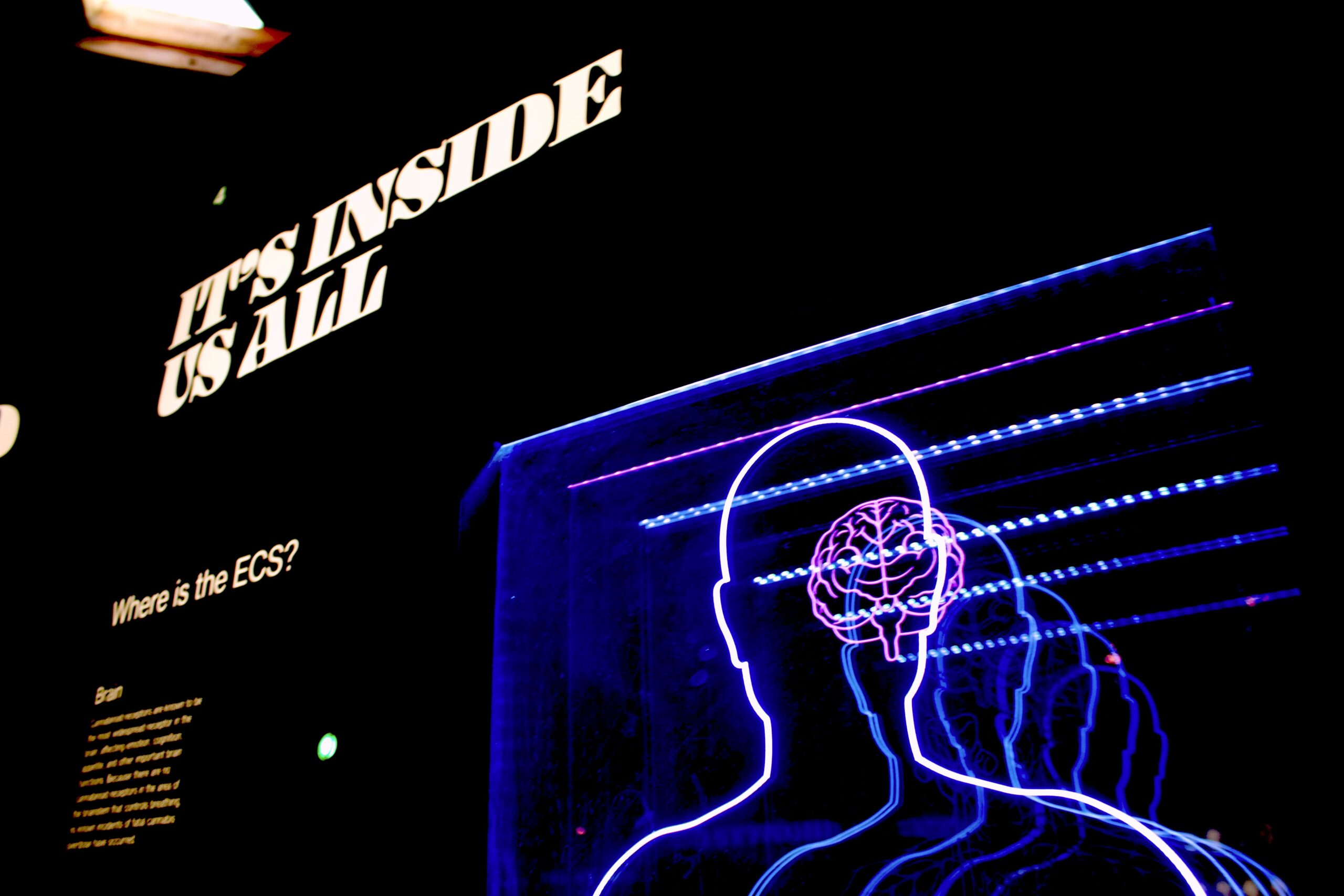


コメント